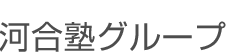教育がその社会にとってどのような影響を与えたのか、どのような成果をもたらしたのかを検証するには時間がかかります。例えば、ゆとり教育が本当に失敗だったのかは、その教育を受けた世代の生涯を見ないと判断できないでしょう。私は、中国の近現代における教育の影響を探っています。特に、現在のような小学校から中学、高校、大学へという近代教育制度が、中国でどのように受け入れられ、その後の中国社会をどのように変えていったのか、中国東部にある江蘇省を事例に検証しています。
日本に留学した中国人や韓国人は母国に何をもたらしたか~東アジア教育交流史

また、19世紀末から20世紀前半にかけて、多くの中国人や韓国人が日本に留学しました。彼らが日本で何を学び、帰国後それぞれの社会になにをもたらしたのか、東アジア教育交流史として研究しています。こうした検証は、今後の教育制度のあり方、あるいは、その国の特徴を探る手掛かりにもなるでしょう。
分野はどう活かされる?
様々なフィールドで、大学で学んだ知識を活かしているようです。例えば、中学・高校の歴史の教員として、特にアジア・アフリカの歴史に詳しく、幅広い知識を授業に活用していたり、旅行会社で中国を担当していたり、中国・東アジアの文献に通じた図書館職員になっている学生もいます。また、中国関係の書店に勤務している学生、アジア関係の博物館で、学芸員として企画・展示を行っている学生もいます。
海外からの日本旅行ブームから一転、新型コロナウィルスの流行で、アジアとの交流も激減してしまいました。だが、コロナ禍が終息すれば、また活発な交流が復活することと思います。大学で修得したアジアの歴史と文化への深い理解は、将来、様々な場面で役立つことでしょう。
明治大学文学部史学地理学科には、アジア史専攻に中国古代史、中国近現代史、朝鮮王朝史、モンゴル帝国史、オスマン帝国史を専門とする教員がおり、西洋史学専攻には近代ロシアの中央アジア政策を研究する教員がおり、日本史学専攻にも東アジアとの関係も視野に研究する教員がいるので、東アジア、中央アジア、西アジアの諸民族、イスラームの歴史が多面的に学べます。またアジア史専攻には1年からアジア史に関する専門授業があり、希望者は教員の引率で海外現地研修(正規授業)に参加できます。

興味がわいたら~先生おすすめ本
李鴻章 東アジアの近代
岡本隆司
李鴻章は、東アジア近代史の転換点となった日清戦争の清朝側の最高指導者。彼は、官僚として出世街道を歩み始めてまもなく、太平天国や第二次アヘン戦争に直面し、近代兵器を手始めにヨーロッパ近代の科学や技術を取り入れる。この「洋務運動」と呼ばれる近代化政策の中で、次の時代を担う新しい人材が育っていく。大まかにいえば、日本の幕末・明治維新と似ているが、社会や政治のあり方が日本と違うため、その展開も異なり、日清戦争の勝敗を分ける。本書は、李鴻章を通じて、日清戦争前後の清朝を描く。日本と中国の近代化を単なる成功例・失敗例と捉えるのではなく、そこから現代にも通じる中国の特徴を捉えようとする点で、本書はアジア史研究の最近のトレンドを代表しているといえる。 (岩波新書)