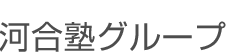第7回 高校生へ 「キミのやりたいことは何だ?」とまず考えてみよう

いろいろと述べてきましたが、私が言いたいことは、どんな社会モデルであろうと、実現する強い意思と明確な目標があれば、CO2は削減できるということです。大事なことは今のしがらみに囚われないこと。今のしがらみに引っ張られると腰が引け、消極的な考えしか出てきません。
星出彰彦さんという人がいます。2013年、国際宇宙ステーションの宇宙の家「きぼう」で124日間の長期滞在を果たした宇宙飛行士です。星出さんの話で有名なのは、子どものころスミソニアン博物館を訪れ宇宙飛行士になりたいと思い、実際宇宙飛行士になったということです。
私自身、40年前、サラリーマンを退職し、国立環境研究所に入った後、約1年なにもしない時期がありました。そのとき「おれ、将来何をしようか?」と考え、国際関係、途上国関係、環境の3つだけは、何があってもやろうと思ったことが今日につながっています。
iPS細胞の山中伸弥先生は「やってなんぼ」というタイプの研究者です。彼の行動力は、高校生自身が未来を考える上で、とてもいい目標になると思います。
僕が高校生にぜひ伝えたいことは、今のしがらみを脱する方法として「おまえは今、いったい何がやりたいんだ?」ということをまず考えてみろということです。それが前にも申し上げた「バックキャスト」という意思決定の方法です。
バックキャストという言葉は、未来を予測する方法として用いる「フォアキャスト」に対する造語のようなものです。今ある材料をもとに未来を構築してみるというのがフォアキャスト。それに対しバックキャストは、まず将来の削減目標を固定し、そこから現在を見返すことによって、目標を達成するためにどのような方策とステップが必要か、その効果や影響はどうなるかを検討することです。温暖化問題研究でいえば、それによって私たちは80%削減が実現できる道筋を示し、社会モデルを描き出しました。
このようにバックキャスト型意思決定の目的は、望ましい将来像を明確にし、その望ましい将来にいたるための戦略を描くことにあります。今の状況にこだわることなく「おまえは今、いったい何がやりたいんだ?」をまず問う。それによって、目標に達するために、どのような手の打ち方が最も効果的なのかを見出す。バックキャストは、強い意志のもとで、あらゆる資源を動員して目標にたどり着く道筋を見つけるための手法なのです。
<おわり>
<前回の記事を読む>
第6回 35年後の5つの社会~キミはどれを選ぶ?

低炭素社会のデザイン――ゼロ排出は可能か
西岡秀三(岩波新書)
エネルギー消費を半減しても豊かな生活は可能だ。二酸化炭素排出抑制によって得られる安定な気候こそ、豊かな生活の基本である。省エネルギー技術、社会インフラの組替え、エネルギー供給システムの革新によって、低炭素社会は実現できる。気鋭の環境システム学者が、ゼロ排出に向けて、今世紀半ばまでに80%削減する現実のシナリオを描く。
低炭素経済への道
諸富徹・浅岡美恵(岩波新書)
今必要なのは、CO2の排出を大幅に削減し、なおかつ経済を向上させる、新たな成長戦略。環境産業政策への転換が必要だと訴える。諸富先生は京都大学経済学部教授。気鋭の環境経済学者と温暖化問題に取り組む気候ネットワーク代表の共著で、低炭素化による経済の大いなる可能性と将来ビジョンを示す。
低炭素社会
小宮山宏(幻冬舎新書)
経済界からは「これ以上大幅なCO2削減は不可能だ」という声があるが、日本の技術力をもってすれば難しくない。「第3章エネルギー消費量の正しい減らし方」では、家庭でのエネルギー、住宅、自動車、新エネルギー、リサイクルなど具体的に提言。元東京大総長。私生活でもCO2削減を実践する環境技術の第一人者が、これから10年の戦略を明快に解き明かす。
原発のコスト――エネルギー転換への視点
大島堅一(岩波新書)
「原子力発電は他と比べて安い」と言われてきたが本当か。実はその計算には、立地対策のために自治体にばらまかれたお金や、放射性廃棄物の処分費用が入っておらず、さらに事故時の莫大な賠償も考えると、原子力は経済的に成り立たない。著者は、福島原発事故が起こる以前からデータを積み上げ実証し、その予見性も話題を呼んだ。立命館大学国際関係学部教授。
水危機 ほんとうの話
沖大幹(新潮選書)
地球の水はいつかなくなるのか? 水資源をめぐって日本も戦争に巻き込まれるのか? 節水はすべて善いことなのか? 著者は、水問題の第一人者であり、温暖化問題・影響リスクの花形研究者。「水はローカルな資源なので、完全市場における競争原理が成り立たない。その結果、水道料金は国内の自治体間で最大16倍もの差がある」といった目からウロコの話も多い。
気候変動+2℃
山本良一責任編集/Think the Earth Project編(ダイヤモンド社)
「2℃」は「人類が超えてはならない一線」。平均気温が2℃上昇すると、社会や生態系が壊滅的な影響を受ける。温暖化の様子をコンピューターグラフィックスで示し、パラパラめくると、1950~2100年まで地球全体の気温が上昇していく様子がわかる。左ページには、温暖化によって想定される被害、新しい温暖化対策の取り組みなどをまとめる。ユニークな切り口の著者は、東京都市大学環境学部教授、元東京大生産技術研究所教授。